中学受験は高校受験や大学受験と違って、子供のやる気を出させるところからスタートしなくてはなりません。
その点では親のサポートが非常に重要になってくるのですが、一向にやる気を出さない子供さんにイライラしていませんか?
今回は、勉強しない子供を見てイライラしてしまう原因と、イライラしないための5つのコツをご紹介します。
スポンサーリンク
勉強しない子供を見てイライラする3つの理由

受験までそんなにもう時間がないのに、一向に勉強に身が入らない。
そんな様子を見ると、ついイライラして「勉強しなかったら合格できないでしょ!」と怒鳴ったりしてしまいますよね。
しかし、親がイライラしたからといって子供のやる気スイッチは入りません。
親の焦りがあるから
親は、中学受験の経験はなくても、高校や大学の受験は経験してきています。
ですから、受験勉強がどれくらい大変かは知っています。
だからこそ、勉強しない子供を見て焦ってしまうんですよね。
そんなんじゃ合格できない、そんな勉強量ではライバルに勝てない。
その思いが「イライラ」となって出てきます。
勉強の仕方への不満があるから
本当に勉強が進んでいるかどうかを確かめる前に、勉強への向き合い方を見て自分が理想としているレベルの勉強量でないと、見ていてイライラしてしまいます。
学校や塾での勉強など、すべてを見ているわけではないのに、目の前の姿だけを見て判断してしまっていませんか?
期待通りに動かないから
学校から帰ってきたら「すぐ」勉強を始めると約束したのに、まだ始めてない!
こんな姿を見ると本当にイライラしますよね。
しかし、子供にとっての「すぐ」は、おやつを食べてからかもしれない。
少し休んでからかもしれない。
親との感覚にはずれがあります。
そんな風に「期待通りに動かない」子供を見るとイライラしてしまいます。
スポンサーリンク
小学生に勉強させることの大変さ

男の子と女の子を比べると、どうしても男の子の方が子供っぽいところがありますよね。
くだらない遊びが大好きだし、勉強なんてめんどくさくてやだー、という子が多いと思います。
子供だってやらないといけないことは分かっているのですが、なかなかエンジンがかからないのですが、それが普通です。
○○さんちの息子さんは塾の宿題もちゃんとやってるのに…なんていう子がいたら、その方が珍しいのです。
ですから、あなたの息子さんが勉強しなくてもそれが普通だと思ってください。
経験していないから焦れない
親は一度ならず「受験」というものを経験していますから、それじゃダメだ!と焦るわけですが、子供からしてみれば一度も経験していないものに対して「焦り」を感じるのは無理なことです。
経験したことがないから受験のイメージもわかないし、勉強しないとどうなるか、落ちるってどういうことなのかも分かりません。だから「焦れない」のです。
ここを理解してあげないと、ただガミガミ怒るだけになってしまい、親の焦りは全く子供に届かなくなってしまいます。
勉強しない子供にイライラしないための5つのコツ

小学校6年生といってもまだ子供です。
将来のことなんて想像もつかない。
だから焦ることが出来ない。
それが分かれば、イライラをそのままぶつけるのではなく、子供が目標に向かって頑張ることが出来るような声かけをしていきましょう。
具体的に話をしてあげることで子供も行動しやすくなりますし、親のイライラも減っていきますよ。
何をどのくらいやらなければいけないかを理解させる
中学受験といっても、受ける学校のレベルによって勉強する量にはかなり差があります。
目指す中学がどのくらいのレベルで、今の学力ではどのくらいの勉強をしないといけないのか、子供自身が分かっていないことが多いものです。
目標と現実の学力にはどれだけのギャップ(差)があるのか、そのギャップを埋めるためには、どれだけ勉強する必要があるのかを明確にしましょう。
たとえば中学受験用の問題集などを見せ、「学校ではやっていないかもしれないけれど、このくらいの難しい問題が解けるようにならないといけないよ、だから今よりももう少し勉強する時間を増やしていかないといけない」ということをきちんと話しましょう。
できることからコツコツと
いきなり模試で高得点をとろうとガミガミ怒っても子供には響きません。
ですから、子供の苦手を把握して、ひとつひとつ克服していくことが必要です。
模試は模試。
あまり点数にこだわらず、本番で最大の力が出せればいい、くらいの気持ちでいてください。
模試の結果は弱点を発見できるいい材料ですから、間違えたところを徹底分析して、間違いをなくすための工夫をさせましょう。
点数を1点でも上げるために、次のようなことを具体的に教えてあげてください。
算数のケアレスミスをなくすために、計算の過程をしっかりと書く
検算は必ずする
問題は最後までしっかり読む
字が汚いことで×にならないよう、書き取りは丁寧に
小さな目標を設定する

勉強の予定を立てることはとても大切です。
予定や目標がないと具体的な行動に結びつきにくいからです。
6年生も後半になると模試を受ける回数も増えると思います。
その模試に向けて、どう苦手を克服していくかという目標を設定すると計画を立てやすいですよ。
計算問題が弱い子は毎日○ページ朝ドリルをやる
漢字の書き取りを完璧にするためにドリルをやる
読解問題が弱いので読書量を増やす(1日○ページ本を読むなど)
やることを決めたら、具体的に毎日の生活の中に予定を組み込んでいきます。
学校から帰ってきたらやること
塾がある日にやること
今月の目標、今週の目標
やらなくてはいけないことをきちんと紙に書き出します。
1日の予定は円グラフにしてもいいですね。
勉強だけでなく好きなことをする時間を確保するためにも、ある程度計画を立てて勉強した方が効率的です。
最初のうちはなかなかエンジンがかからないかもしれません。
しかし、1つでも予定通りに出来たら褒め、次の日も継続できるように声かけをしていきましょう。
具体的に伝える
子供はやっているつもりでも親から見て「やる気がない」と見えることはしばしば。
しかし、子供からしてみれば「ちゃんとやってるのに」と反発したくなります。
ですから、集中して勉強して欲しいなら、「○時まではテレビを見ないでやろう」「そのくらいの問題量なら○分で終わるね」など、具体的に何をして欲しいのかを伝えましょう。
頭ごなしに叱らない
なんで勉強しないの!と頭ごなしに怒ってしまうと、余計にやる気がなくなります。
「今やろうと思ってたのに」と、反発心しか起こりません。
今日は何時から始めるんだっけ?
今日はどの問題集をどれだけやるんだったっけ?
などと、穏やかに聞いてみてください。
中学受験をさせる意味をもう一度考える
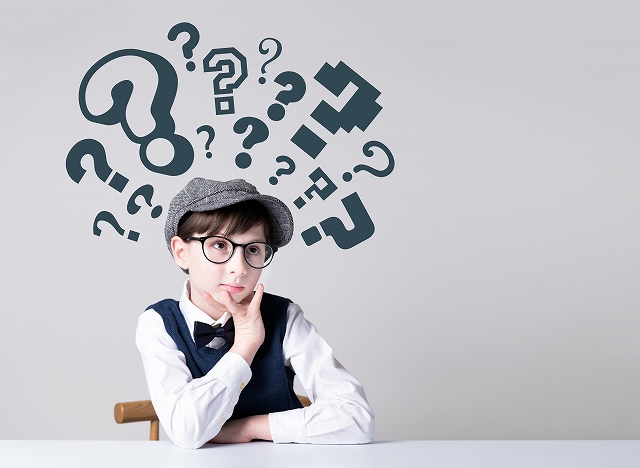
中学受験をしたい!と自ら言い出す子は少ないと思います。
親が受験させたいと思って勉強させているケースが多いと思いますが、子供の意識は今どこにあるでしょうか。
学校へ通うのはあくまでも子供であり、「この中学校へ行きたい」という子供の気持ちが何より大事です。
その気持ちさえあれば、自然とやる気もわき起こってくるものです。
勉強しない姿にイライラしているなら、「この中学校へ行ったらどんな中学生活が待っているんだろう」と具体的な未来像がイメージできるようにしてあげてください。
学校見学に行くとか、その学校を卒業した人たちはどんな職業についているのか、など卒業生にどんな人がいるのか調べるのもいいでしょう。
中学校までは義務教育で労せず進学できるのですから、あえて大変な受験勉強をさせてまで違う中学校へ行かせる意味をもう一度親子で考えてみてください。
まとめ

小学6年生はまだまだ遊びたい盛りです。
勉強したくないのが普通です。
だからあまりイライラしないでください。
それよりは、親が心に余裕を持って、勉強って楽しいよ、受験に合格したらこんな中学生活が待っているよ、という未来像、将来像をイメージできるように楽しい話をしてあげた方がいいでしょう。
