「うちの子、学校の授業中にノートを取らないんだけど大丈夫かしら?」と不安に感じたり、子供の学力的な将来を心配をしている親御さんがおられるかもしれません。
今回は、論文やデータなどはありませんが、私が大学時代に行った家庭教師から、非常勤講師や塾講師などを経て、これまでに教えてきた数々の児童や生徒を見てきた経験から、その様子をふまえて、経験に基づく話をさせていただきたいと思います。
あくまで経験論ですので、ご了承ください。
スポンサーリンク
ノートを取らない子の特徴

ここからは、私がこれまでに出会った子供たちのなかで、ノートを取らないタイプの子の特徴です。
面倒くさい
身体を動かすことや遊ぶことが大好きだけど、勉強はやりたくないという元気なタイプ。
ノートを取るにも、鉛筆が削ってなかったり、消しゴムが無かったり、字も汚いので根本的にやる気が出ないという子がいます。
面倒くさい子には、小さな達成感を楽しめるように誘導できると良いですね。
ノートを取る意味がわからない
中には、必要性を感じていない子もいます。
有名な心理学関連の書籍でもよく言及されますが、人間の行動の背景には、必ず目的や理由があります。
子供をはじめ、大人も、誰もが何かの理由があって行動をしています。
ノートを取る意味が分からない子や、ノートを取る必要性を感じていない子は、ノートを取らないです。
子供は、「なぜ?」という疑問をたくさんもっています。
「なぜ食事の前には手を洗うの?」という問いに、
「手には細菌がたくさんついているから、食事と一緒に口に入ってしまって、自分が病気にならないようにするために手を洗うんだよ!」
と答えれば、子供は納得して手を洗うようになります。
「なぜノートを取るのか?」という問いに、
「ノートを取らないと先生に怒られるよ!」といった恐怖を呼び起こすような理由ではなく、子供が自発的にノートを取りたくなるような目的を一緒に見つけてあげられると良いかもしれません。
進学を諦めている
落ちこぼれていると自分で思い込んでいる子もいます。
私は本来、「落ちこぼれ」というのはいないと思っておりまして、本人や先生、家族の思い込みではないかと思います。
自分は勉強についていけないし、進学できないと諦めてしまっていると、目的を失ってしまっていますから、ノートを取るどころか、学校生活自体が苦痛となってしまいます。
このような状態の子に、いくら「ノートを取りなさい」と伝えても、的が外れていますから逆効果です。
まずは、本人が自分の状態に気づき、受け入れ、そして、前向きに進学に向かえるような対応が必要だと思います。
ノートの取り方がわからない
単純にノートの取り方がわからない子もいます。
先生によって、授業スタイルは異なります。
ある組の先生は、黒板にすべてわかりやすく書いてくれるため、多くの子供がノートを取りしやすかったりします。
別の組の先生は、黒板は最小限のポイントだけ書いて、後は、お話を中心に授業をするということもあります。
担当される先生によって、授業スタイルは異なりますから、クラス替えや先生の交代が起きた時点で、ノートの取り方がわからないという子も出てくると思います。
ノートを取らなくても大丈夫なほど理解している
中には、授業が簡単すぎて頭に入っているから、なぜノートを取らないといけないのかわからないという子もいます。
優秀であるがゆえに、ノートを取る意味が分からないタイプです。
先生の話を、黒板は目で見て、耳で聞いて、わかってしまう子がいます。
もうわかっているのに、なぜわざわざノートに書かないといけないのかという主張です。
ノート取らない子の中には、塾やウェブ授業で先取り学習していたり、すでに予習が済んでいる場合が考えられます。
すでに学んでいて知っていることの復習を授業中に行っているので、よくわかっているためノートを取る必要性を感じられないわけです。
このような場合は、ノートを取らなくても、ワークやプリント、宿題のドリル等でおさらいが十分できますから、授業中にノート取らなくても、小学生の間であれば十分大丈夫だと思います。
自主学習ノートなど、家庭で学習できること、自分で作っていれば、特に問題ありませんし、本来、ノートを取ることが目的ではないですし、理解することが目的ですから、手段はどうであっても良いでしょう。
ノートを取れない子の特徴

ノートを取りたいと思っていても取れないタイプの子も、クラスに少数ではありますが、一定数います。
授業についていけていない
病気で長期的に学校を休んでいたり、発達障害や学習障害など、何らかの特徴や性質、個性があってノート取れない子もいます。
通常の学校のクラスで一斉授業をするより、個性や特徴に合わせた個別指導を必要とするかもしれません。
字を書くのが遅い
字を書くことが苦手な子も少数派ですがいます。
文字を認識することが苦手な子や、字を書くときに、平均よりも何テンポか遅い子に関しては、授業中に書き写すことだけで手一杯で、授業を聞くことに集中していないことがあります。
学校の先生は、大抵は授業を平均的な子に合わせますから、いつもこのような子は中途半端な状態となってしまいます。
別途、個別トレーニングが必要かもしれません。
ノートを取っているのに成績が悪い子の特徴
ノートをきれいに取っているのにも関わらず、成績が悪い子もいます。
傾向として、女の子に多い気がするのですが、ノートを取るのが楽しくて、色を使ったり、さまざまなイラストを描いたりして、授業を聞いていないタイプです。
ノートを取ることが目的となっていますから、ノート自体の見た目やクオリティは高いのですが、授業を聞いておらず、本質を理解していません。
一生懸命にノートを作っただけで、頭に入っておらず、勉強をやった気になっているパターンの子は、テストを受けても点数があまり良くないです。
ノートを取ることは本当に必要なのか?

ノートを取ることは、本当に必要なのでしょうか?
結論から申し上げますと、ノートを取ることは、手段であって目的ではないと思います。
学んだことが頭に入って、社会に出ても応用できるレベルで理解できることが目的であるなら、手段はノートを取ることでなくても良いと思います。
1回先生の授業を聞いて、先生が黒板に書いたこと、話した内容が全て頭に入る子であれば(そのようなタイプの人も一定数はいるようですし)、ノートを取る必要は全くないでしょう。
また、例えば、授業を録音してくり返し聞いて頭に入るのであれば、それで良いと思います。
ただ、誰にでも1日の時間は24時間と限られていますから、学校で1日のうちに数時間受けた授業を何回も聞いて理解するとなると、相当な時間を必要としますね。
2020年現在、日本の教育システムの中では、授業を受けた内容をノートに取って学習することが、中間期末テストや高校受験や大学受験に役立つ方法であるから、ノートを取っているという人が多いのではないでしょうか。
このような時、授業で教わった内容を素早く思い出すために、ノートを取っておき、後で復習がすぐにできれば、学習時間を効率良くし、短い時間で高いレベルの勉強時間を確保できますね。
私は、もしこのようなノートの取り方ができていれば理想的で、効率よく学習ができるお子さんだと思います。
また、そのようなノートの取り方を身につけていれば、大学に入った時も困ることは無いでしょうし、社会に出て、新しい仕事を覚える際にも、その人の成長速度は早くなるのではないかと思っています。
もしも、「ノートを取れ!」と先生に言われるから、仕方なくノートを取っている人がいたら、いくらノートに書き留めていても、それはあまり効果的ではないでしょう。
「どうすれば、効率よく学ぶことができるか?」
「習ったことを誰かに教えてあげよう!」
そのようなことを考えながらノートの取り方を工夫してみると、ただ授業を聞いてノートを書き写しているだけの状態より、数段授業を楽しめると思います。
現在の日本の教育システムの中で、大学進学を目指している場合は、大学生になっても、社会人になってもずっと役立つ効果的なノートを取る方法を知っておくべきだと思います。
ノートを取る必要性・まとめ
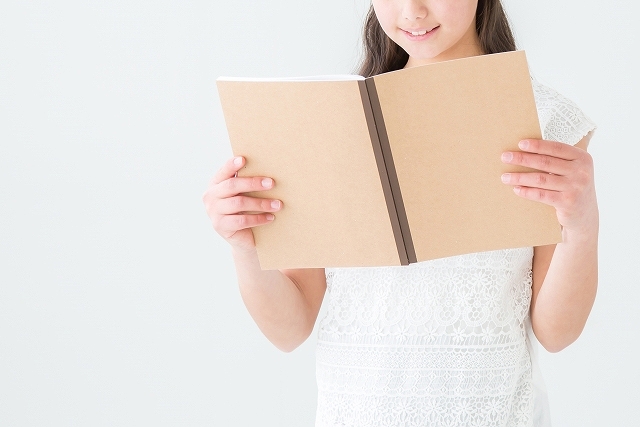
これから訪れるAIの時代、インプットに関しては、人間はコンピュータに勝てないです。
凄まじい量のデータベースから何かを探せるAIには、人間はかないません。
今後の教育に必要とされることは、AIには苦手なことをできる人間を育てることでしょう。
知識をインプットしてテストの点数が良ければ良かったこれまでの時代は大きく変わり、今後は、無から何かを作り出したり、表現したりできることが、これからはより重要視されるでしょう。
論理的な思考力や、情報分析力、表現力や創造力、コミュニケーション力などを伸ばしてゆかないと、将来優秀な人材として活躍できるかどうか心配になります。
たかがノートと思われるかもしれませんが、小さな第一歩として、ノートの価値を見直してみてはいかがでしょうか?
