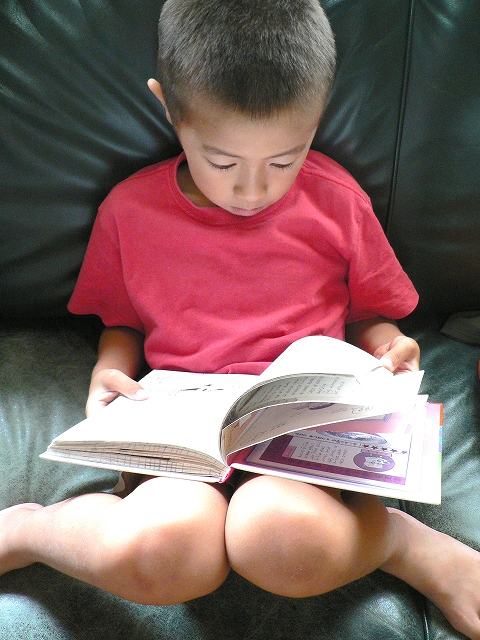読書のメリットは数えきれないほどあるのですが、「それはわかってはいるけれど、読書は苦手なんだよね・・・」という子供さんや親御さんも多いのではないでしょうか。
特に、子供の読書を見ていて、読むスピードが遅いのではないかと感じて心配しているパパやママもいらっしゃるかもしれません。
今回は、読書が遅い原因や、小学生の間から読書習慣をつけるアイデアについてまとめてみました。
スポンサーリンク
読書が遅い5つの原因
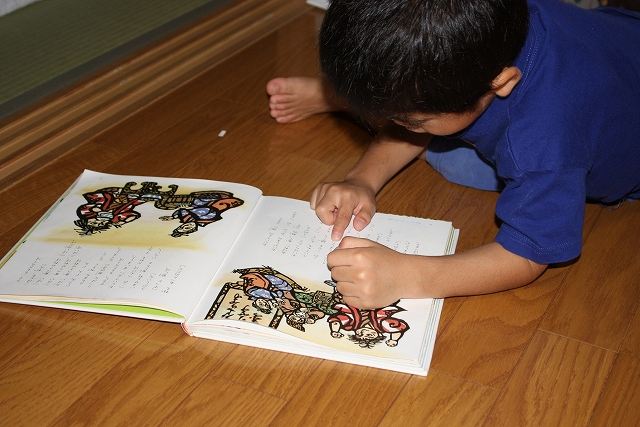
子供の読書が遅いと感じられる原因には、どのようなものがあるのでしょうか。
あくまでも、考えられうるいくつかの原因ですので、他にもあると思います。
国語力が足りない
子供の現在の国語力よりもレベルの高い言葉などが出てくる本であれば、国語力や読解力が足りず、なかなか読み進められないというケースがあります。
例えば、パパやママなど大人に置き換えてみると、スペイン語を習いたての状態で、スペイン語の絵本を読もうとして、早く読めませんよね。
スペイン語の能力がアップすればするほど、長文を読む速度や読解力もついていきます。
子供にとって、本を読んでいる時に、難しい言葉に出会ったり、読めない漢字に出会ったりすると、そこで「わからない・・・」という気持ちになり、特にきちんと理解したい完璧主義タイプの子にとっては、やる気がなくなってしまうということもあるでしょう。
知らない漢字が多くて、子供にとって一般的なが新聞が難しくてなかなか読めないように、子供の国語力に即したレベルの本であればそれなりの速度で読めるのかもしれません。
読書の経験が少ない
そもそも本を読むことに慣れていない、ほとんど本を読んだことがない、という子にとっては、読書スピードは遅くなると思います。単に経験が足りていないからです。
たくさん本を読む子が読書スピードが速いかというと、すべてに当てはまるわけではないと思いますが、経験が多い分、知識が豊富になり、出会う言葉や語彙も多くなりますから、読解力は上がっていきます。
自転車に最初から乗れる子はほとんどいませんし、補助輪からスタートしますね。
スイミングでも、最初から泳げる子もいないですし、ピアノも最初から上手い子はいません。
読書も、経験を増やすことでスキルアップができるものの一つだと思います。
気が散っている
読書には集中力が必要です。
周りに様々な誘惑があって、集中する環境になっていなければ、読書をしているように見えても、全然集中していないということがあります。
早くゲームをしたいとか、早くおやつを食べたいとか、そのようなことを考えながら読書をしても、頭に入っていかないです。
読まされている
本当は読みたくもないのに、学校の先生が「読んできなさい」と宿題を出したから読んでいるとか、親が「これを読みなさい」と渡してきたから、本当は興味がないけど、読んでいるとか。
イヤイヤとまではいわないまでも、読まされているという気持ちがあれば、読むスピードが遅いのもやむを得ないでしょう。
文字を認識する力が弱い
人数は決して多くはないですが、文字をきちんと文字として認識できないタイプの特徴を持っている子もいます。
その場合は、文字の読み書きが、とても遅かったり、他の子に比べて極端に苦手だったりします。
スポンサーリンク
読書の習慣をつける6つのコツ
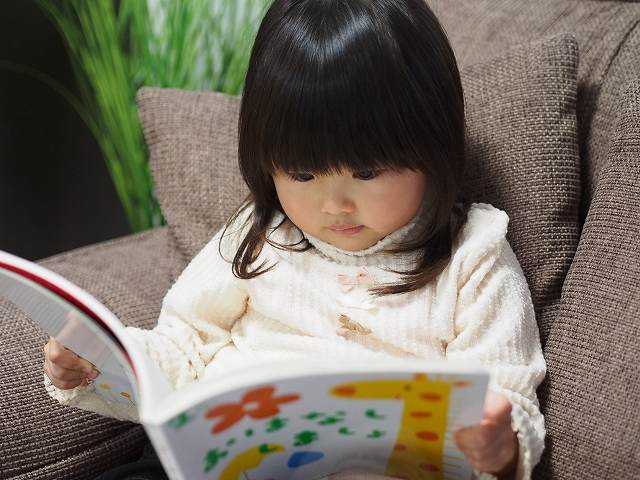
読書において、読むスピードが遅いことは、子供のうちはそれほど問題ないと思います。
読書のスピードが早くても頭に何も残っていなければ意味がありませんし、きちんと内容を理解しているという事実があれば、スピード自体はさほど気にする必要はないでしょう。
むしろ、本を読むことが楽しいという気持ちを大切にしてあげることが大切ではないかと思います。
読みやすい簡単な絵本や本をくり返し読む
小学生なのに、幼児向けの絵本を与えるのは、ちょっと気が引けると思われるかもしれませんが、読みやすいレベルの本で、気に入った本があれば、それをくり返し読むことはおすすめです。
内容をすでに知っている絵本であれば、抵抗なく読めますし、難しい言葉も出てきませんから、子供にとっては楽しい読書となります。
また、子供はくり返し同じ本を読むことが好きだったりします。
好きな絵本の好きなページを何回もくり返しめくって喜んで読むこともありますね。
本が好きだ、という気持ちを大切にして、絵本だから幼稚だとか、あまり深くは考えず、子供が好きな本を読ませてあげるということが良いのではないかと思います。
大好きな分野の本を読む
ゲームが好きな男の子だったら、ゲームの攻略本を隅々まで読みまくるということは楽しいと思います。
子供は、自分の好きなことや興味のあることに対しては、ものすごく集中力を発揮することがあります。
没頭すると言っても過言ではありません。
例えば、テレビゲームが好きな子供が、毎月届くゲームの月刊誌を隅々まで読みあさり、知らない漢字を全て辞書で調べながら読んだことで、読解力がついたという子もいます。
詩やリズムの良い本を音読する
子供は、詩とか音楽リズムが大好きです。
こんな本のこんなフレーズを、なぜ子供はこんなにくり返すことが好きなのだろうか?と不思議に思われるかもしれませんが、子供はくり返しが好きです。
良いリズムのフレーズや、覚えやすい詩など、音読することが好きな子供は多いです。
また、子供は気に入った本を何回も音読するものです。それほど、子供はくり返しが大好きなのです。
なぜかと言うと、「くり返し」は、「自分ができること」だから楽しいのです。
かけ算の九九も、できるから楽しいと思って、何回もくり返すのです。
「できないこと」は楽しくないですが、「できること」は、子供にとってとても楽しいことだということです。
自分で読みたい本を選ばせる
効果的な読書は、やはり、読まされて読む読書ではないと思います。
何かしら興味があって読んでみたいこと、自分が手に取って、「これを読んでみたいな」と思った本など、そういう本をすすめてあげたらと思います。
そのためには、本屋さんや図書館に行くことを定期的なスケジュールに組み込んだりすることも良いですね。
また、子供から「今度は、こんな本が読んでみたい!」といった発言が出るように、普段から、新しい本の話題や、読みたい本や、興味のあることについて話題を出してコミュニケーションのネタにしておくことも大切ですね。
パパやママが読み聞かせをしてあげる
読み聞かせにはさまざまなメリットがあります。
親子の貴重なスキンシップの時間でもありますし、できるだけ楽しい雰囲気で読書タイムを盛り上げてはどうでしょうか。
パパやママが読んでいる間でも、子供にセリフを読んでもらったり、交代して読んだりしながら、一緒に本を読むという時間を作ることで、読書が大好きなお子さんになるかもしれませんね。
また、パパやママが普段から読書をしている姿を見せておくことも、良い影響を与えるでしょう。
読んだ本の感想を言い合ったりできるなど、読書好きな親御さんの子供は、読書に対して良い印象を持つことでしょう。
読書日記をつける
読み聞かせの流れで、もし毎日、もしくは、週に1~2回でも、読書をした時に、読書ノートや読書日記をつけるということも、習慣化させる上で効果的です。
子供は、何かを達成したご褒美にシールを貼ったり、スタンプを押したりすることが好きですね。
例えば、読んだ本のことについて、一行でも良いので短い感想を書いて、シールを貼るといった習慣化でも良いです。
また、今日は5ページ読みました、ということで、読んだことを重視して、スタンプを押してあげたり、シールを貼ってあげたりすることも、子供にとってはワクワクするかもしれません。
読書の習慣化という目的で、「100冊読書日記」という書籍がありますので、リンクを貼っておきます。
小学生から読書習慣をつけるコツ・まとめ

今回は、読書の遅さについての原因や、読書を習慣づけるためのコツなどをご紹介しました。
子供は、放っておくと、ゲームや遊びにどんどん流れていきます。
自分で自分をコントロールできるようになるには、まだまだ未熟ですから、パパやママのサポートが大変重要です。
読書のメリットはたくさんありますので、子供さんが読書好きになって、いろいろな知識や教養を自分から得られるようになるまで、小学生の頃からのサポートは大切です。
親御さん自身も、子供と一緒に読書を楽しむ感覚を大切にしていただければと思います。