生きてくためには忍耐力が必要です。
すべてが思い通りにはならないし、何でも手に入ることなんてあり得ません。
忍耐力は子供のうちから身につけさせないと大人になってから身につけることはなかなか難しいものです。
ではいくつくらいから、どうやって忍耐力を身につけさせればいいのでしょうか。
スポンサーリンク
そもそも忍耐力とはどういうものか
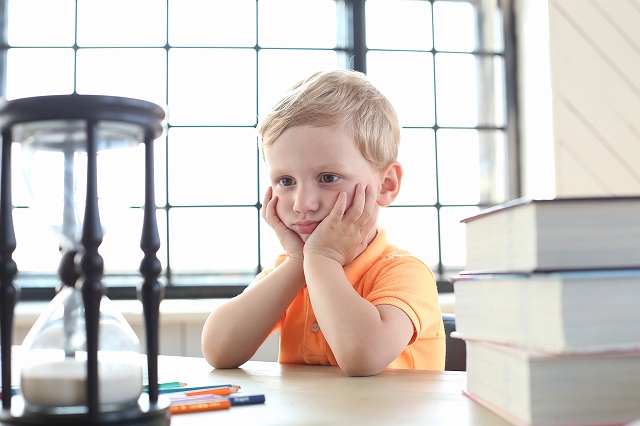
忍耐力とは、イヤなこと、辛いことを我慢する力、苦しみに耐える力。
精神力の強さです。
子供はもちろん、大人になっても生きていくためにとても必要な力です。
辛いからといってすぐに逃げ出すのではなく、それをどう乗り越えたらいいだろうかと試行錯誤する力でもあります。
忍耐力がないとどうなるか

忍耐力がないと、ちょっとしたことで諦めてしまったり、何事も長続きしないという大人になってしまいます。
特に社会に出て仕事をするようになると、楽しいことばかりではありません。
次から次へと難題が降ってわいてくることもあります。
その度に逃げ出していたら仕事ができません。
人間関係においても同様です。
人にはそれぞれ長所や短所があります。
社会に出たらみんな友達ではありません。
つき合いにくい人とも仕事の上でおつき合いしなくてはいけないことだってあります。
その時に、どうすればお互いにとって良い関係を築けるかと前向きに考える人と、面倒だから、イヤだからと放り出してしまう人では、人間関係の作り方が全く違ってきますね。
忍耐力はあってもそれほど困ることはありませんが、ないと困ることがたくさんあります。
忍耐力はいつから身につけさせるべき?

子供は忍耐力がないものです。
なくて当たり前。
ではいつから身につけさせればいいのでしょうか?
スポンサーリンク
言葉がわかるようになる頃
自分ではたくさん喋ることが出来なくても、子供は大人の言うことを結構理解しているものです。
1歳当たりから、話は出来なくても親の言うことを少しずつ理解できるようになります。
早い子供なら1歳過ぎた当たりからちょっとずつ喋りだしますね。
2歳くらいになるとだいぶ色々な単語が出てくるようになり、少し文章のような長い言葉も話せるようになります。
ですから、だいたい2歳前後、親とコミュニケーションがとれるようになったなと感じたら、我慢することを教え始めてもいいのではないでしょうか。
繰り返し、繰り返し教えること
子供は1回、2回言ったところですぐに出来るようにはなりません。
まさに親の忍耐力が試されるところですが、無理強いするのではなくて、大事だと思うことを繰り返し話していくしかありません。
なぜ今我慢しないといけないのか
なぜこれをやらなければいけないのか
その理由を繰り返し話します。
怒ってしまうと「怒られた」という感情しか残りません。
頭ごなしに叱るのではなくて、何度も何度も話をしましょう。
子供に忍耐力をつけさせる4つの方法

子供に忍耐力をつけさせるためには、愛情を持って、そして時には厳しく接することが必要です。
欲しいものはルールを決めて与える

おもちゃやお菓子など、子供が欲しがるものを何でも与えるのではなく、一定のルールを決めて与えるようにしましょう。
ルールの決め方は、家庭によってそれぞれの考え方があると思います。
お金の価値観も違いますし、これが絶対正しいというものはありません。
たとえば、次のように何か努力したことに対する報酬として、欲しいものを買ってあげる基準を決めます。
家のお手伝いをしたら1つにつきシールを1つ
自分で早起きできた日はシールを1つ
本(または絵本)を1冊読んだらシールを1つ
シールが10個たまったらスーパーでお菓子を1個
これは、子供と話し合って決めるのがいいでしょう。
ただ、決めたルールは親の気分で変えることなく、きちんと忍耐力を持って守るようにしましょう。
失敗しても見守る

子供うちは色々なことをやってみて、失敗するという経験がとても大事です。
むしろ、失敗が許されるのは子供のうちだけなのですから、たくさん失敗して、その中からたくさんのことを学んでいくことが強い心を育てます。
ついつい親が手を出して失敗を防いでしまったり、それはあなたに向いていないとか危ないとか色々な理由をつけてチャレンジさせなかったりしますが、それは子供の成長の芽を摘んでしまうことになります。
何かに失敗しても、頼れる親がいれば大丈夫です。
そして、自分の力で立ち直れるように、親は愛情を持ってじっと見守ることが大切です。
読書をさせる

本を読むというのは、テレビでマンガを見ることと違って、とても忍耐力を必要とします。
絵本であればまだしも、文字だけの本となるとかなり疲れます。
文字を目で追い、話を理解しながら次のページに進まなければいけないからです。
小学校に入学する前だったとしても、文字が読めるようになれば、親が読み聞かせをするだけでなく、子どもに読ませてみるといいでしょう。
「読んで聞かせて」というと、最初は意気込んで始めるものの、数ページで飽きてきます。
面倒だからです。
スラスラ読めないことにもいらだちを感じて、途中でやめようとしますが、毎日やっていると段々読める量が増えてきて、自分が読むこと自体にも楽しみを覚えるようになってきますよ。
習い事を通じて忍耐力を養う

幼稚園、保育園、小学校低学年あたりの年齢だと、じっと座っていることすら難しいこともあります。
忍耐って何?という年齢です。
学校では今あまり厳しく指導しない傾向があるので、忍耐力は家庭でしっかり身につけさせる必要があるでしょう。
小学校に入る前から出来る習い事のひとつにそろばんがあります。
そろばんは週に2~3回通うことが普通で、他の習い事に比べると通う頻度の高い習い事です。
しかも、教室に行った時だけやるのではなくて、家でも練習する必要があります。
そのためには、見たいテレビも我慢して、練習問題を解かなくてはいけません。
力をつけるためには練習するしかなく、練習するためには今やりたいことも我慢しなければいけない。
そういったことを普段の生活の中に組み込んでいくことで、自然と忍耐力が身に付いていきます。
ピアノや英語など、やはり家での自主練習が必要な習い事であれば、同様に忍耐力をつけていくことができるでしょう。
実は親の姿が一番大事

色々と子供に忍耐力をつけさせる方法を紹介しましたが、そもそも親に忍耐力があるか?ということについて、今一度考えてみてください。
一緒に暮らしている親に忍耐力がなかったら、口先であれこれ言っても子供に伝わるでしょうか。
子供に忍耐力をつけて欲しい、強い気持ちを持って生きていって欲しいと思うなら、自分自身が忍耐力を持っている必要があります。
ちょっとしたことで腹を立てて子供を怒鳴り散らしたり、子供がうまく出来ていない様子を見てつい口を出してしまったり。
大人も忍耐力が必要な場面がたくさんあると思います。
子育てはイライラすることの連続ですし親も人間ですから、すべてにおいて忍耐力を発揮できるかといったら決してそうではありません。
しかし普段から「親にも忍耐力が必要だ」と思っているかどうかということは、子供にも影響を及ぼすでしょう。
やっぱり子供は親の背中を見て育つからです。
子供に忍耐力をつけさせる方法・まとめ
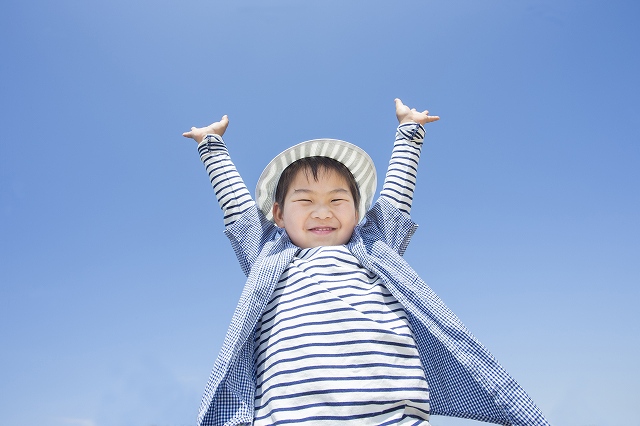
社会に出れば、親に頼ることなく自分の足で立って生きていかなくてはいけません。
昔のように名の知れた大学に入れれば、それなりの企業に就職できて一生安泰、なんてことはないのです。
今ある職業の半分は10年後になくなるとも言われています。
もしかしたら、とりあえず会社員、なんていう働き方すらなくなるかもしれません。
だからこそ、自分で生きていく力が必要です。
どんなに辛いこと、大変なことにもめげない、強い気持ちを持った大人に育てるには、子供のうちからしっかり種を蒔いておく必要があります。
