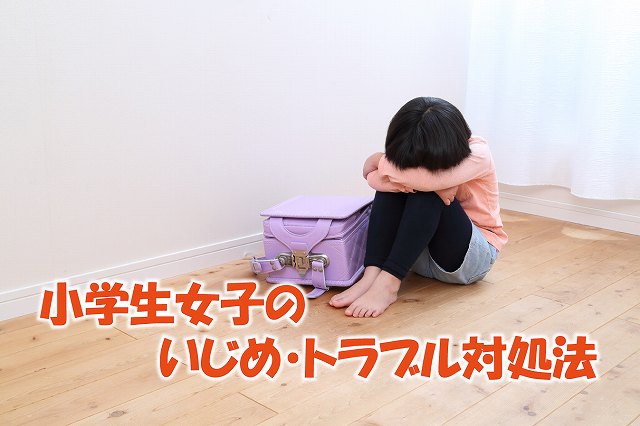いじめは中学校、高校で問題になることが多いですが、最近は低年齢化が進み、小学校でもいじめの問題が起こっております。
男子のいじめも深刻ですが、小学生女子のいじめやトラブルは、男子よりも悪質で陰険であったりします。
いじめを受けている子の中には、親や先生に知られてしまうことで、更なる報復を恐れて、悩みを言えない子もいます。
小学生女子のいざこざは面倒くさい、とよく言われますが、実際にいじめを受けて苦しんでおられる子供さん、親御さんの助けに少しでも貢献できればと思い、いじめやトラブルへの対処法をまとめてみました。
スポンサーリンク
いじめる側の主な原因

実際にいじめる子と、加わる子、傍観者的な存在もいますが、主な心理的な要因は以下のものが挙げられます。
優越感にひたりたい
自分をアピールしたい、一番になりたい、人よりも勝りたいという感情から、誰かをいじめてしまう。
自分に自信がない子や、コンプレックスのある子が弱い者いじめをしてしまうケースがあります。
ストレス発散
家族内でのいざこざや、好きな男の子が振り向いてくれないなど、恋愛などの人間関係で思い通りにいかないと、日常的なストレスがたまります。
イライラをぶつけるストレス発散のために、いじめが起きたりもします。
虐げられた経験がある
人間は、無意識に、されたことをしてしまうという特徴があるようです。
虐げられた経験のある子は、経験をもとに、それを人に対しても行ってしまうことがあります。
自分が次のターゲットになることを恐れる
ボスに目をつけられたら、次のいじめのターゲットになってしまうかもしれません。
集団と同じことをしないと、その集団から外され、自分がターゲットになってしまうという恐怖から、自分の気持ちとは裏腹に、いじめに加担してしまうケースもあります。
ゲームやテレビの影響
ゲーム感覚でお友達をからかってしまったり、テレビのバラエティ番組などのふざけるノリを真似する感じで、お友達に失礼なことを言ってしまったり、いじめに発展してしまうケースもあると思います。
思いやりや罪悪感の欠如
祖父母と3世代同居などの生活することが少なくなり、核家族化や両親の共働きが増え、思いやりや罪悪感などを生活の中で学ぶ機会が減少しています。
悪いことをしているという感覚自体があまりない子には、良いことと悪いことが何かということから教えてあげなくてはなりません。
どうしたら良いか分からない思考停止
とりあえず傍観し、何もしないで見ているタイプの子もいます。
安全策として、人数の多い方に同調しておくというケースです。
スポンサーリンク
いじめのターゲットになりやすいタイプ

小学生の女の子は、同年代の男子よりもませていたりしますし、恋愛などの嫉妬の感情が強かったりします。
いじめを受けやすいタイプのお子さんの特徴を挙げてみました。
外見がみんなと違う子(髪の毛、体型、不潔など)
目立つ子(勉強ができる、スポーツができる、可愛いなど)
男の子にモテる子
自慢する子
無口やおどおどしている子
反応が面白い子
浮いてしまうタイプの子(空気を読めない、協調性に欠ける)
発達障害などコミュニケーションが苦手な子
陰険ないじめの例

子供は正直で、善悪の区別なく、人を傷つけることを言ってしまうことがあります。
大人と違って、感情をコントロールすることに慣れておらず、悪質な行動に出てしまうことがいじめにつながります。
以下は、女の子に多い、陰湿ないじめの例です。
仲間はずれにする
汚いもの扱いする
くつや持ち物を隠す
ものを奪う・ゴミ箱に捨てる
1人だけ無視する・誘わない
クラスメイトに悪口を言いふらす
意地悪な手紙を書く
嫌がるあだ名をつける
教科書などに落書きする
嫌味や悪口を本人に聞こえるように言う
親ができるいじめ予防・早期発見の工夫

いじめに遭わないことが一番良いのですが、どこの学校でも一定数のいじめは発生しています。
大きな問題につながる前に、できるだけ早くトラブルを発見して、早期対処したいものです。
日頃からの十分な親子のコミュニケーション
両親共働きともなると、なかなか子供の小さな変化に気づいてあげられないこともあるかと思います。
しかし、子供のSOSサインにいち早く気づくことで、大きなトラブルにつながることを防ぐことができるでしょう。
例えば1例ですが、食事は必ず一緒にとり、食事中にはテレビを見たりせず、家族の会話を楽しみましょう。
学校でどんなことがあったのか、どんなお友達がいて、何をして遊んだのかなど、普段からこまめにコミュニケーションをとることで、子供に起きているトラブルを早期発見することができます。
以下の3つのことを心がけて子供の話を聴くと、多く話してくれるようになってゆきます。
-
最後まで聴くこと
-
途中で否定しないこと
-
うんうんと共感すること
「そういえば、最近、仲良かった〇〇ちゃんの話を聞かないけど、〇〇ちゃんは、元気にしてる?」
こういった何気ない質問に対して、娘さんの反応が薄かったり、口ごもったりするようでしたら、要注意のサインです。
普段から、子供の様子をよく観察し、何でも話せる関係をしっかり築いておけると良いと思います。
子供の心が閉ざされている時の会話のコツ
子供の語彙力は少なく、感情をうまく表現できない子供さんもたくさんいます。
そのような時は、親が代弁してあげると子供の気持ちを楽にしてあげることができたりします。
子供の心が閉ざされている時は、「はい」「いいえ」で答えられる質問をすると良いです。
言いたくないことがある時でも、YESかNOは言えます。
「夕食できたけど食べる?」
「ママと一緒にお買い物行く?」
心がほぐれるまでは、YES NOだけでも良いので、意思表示を確認しながら、まずはお互いの信頼関係を築いていきましょう。
学校で辛いことがあった時などは、
「学校で、お友達と仲良くできないことがあって、悲しい思いをしたの?」
「仲良くしていた〇〇ちゃんと、別のお友達が仲良くなってしまって、つらい思いをしているの?」
子供の気持ちを、親が代わりに代弁して表現し、子供にイエス、ノーで答えてもらうことで、気持ちを楽にしてあげることもできます。
パパやママは、私の気持ちをわかってくれたということで、少し心が軽くなると思います。
本人がいじめと戦うための6つの対処法

子供さんの性格にもよりますので、誰にでも当てはまることではありませんが、いじめられている方の対処法の例です。
反応せず、気にしないそぶりで堂々といる
リアクションがなければ、いじめる側にも何も楽しみがありません。
反応が楽しくてからかったりすることも多いため、無反応で堂々としているようであれば、つまらなくなっていずれやめてしまうでしょう。
どんな友達に対しても親切にする
悪い人間には、必ず罰が当たるようにできているので、自分だけは悪い人間にならないと決めて行動するようにしましょう。
困っている子がいたら、助けたり声をかけたりしましょう。
自分はたとえいじめられている人間だとしても、仕返しをしたり、他の人をいじめたりはしないように人間を磨きます。
悪いことには同調しない
たとえ、自分の次にいじめのターゲットになる子が現れても、自分は絶対に同調したり、友達に誘われて乗ったりしないでおきましょう。
悪いことは、いずれ必ず自分にはね返ってきます。
良い本を読み悪に屈しない精神力を身につける
歴史上の人物の中で、すさまじいいじめや試練にも負けず、偉大な人生を歩んだ人は数えきれないほどいます。
そのような偉人の本をたくさん読み、受けた苦難やそれを並々ならぬ努力で乗り越えてきた過程を学びましょう。
勇気を与えてくれる伝記は、図書館でたくさん見つけられます。
得意なことに打ち込み10年後にいじめっ子を見返す
自分に自信がない子供さんは、何か一つで良いので、自信をつけられる何かに取り組んでみましょう。
勉強でもスポーツ、楽器や表現する習い事など、何でも良いです。
何か一つ、好きなこと、得意な分野を見つけて、それに取り組んでスキルアップする努力してみましょう。
小さな努力の積み重ねが、自分の自信につながります。
自分に自信がついてゆけば、怖いものや不安が少しずつ減ってゆくことでしょう。
友達を1人作る努力をする
友達をたくさん作る必要はありません。
しかし、友達が1人いるかどうかで、学校の楽しさは大きく変わります。
例えば、とても静かでいつも一人でいる子、過去にいじめられた経験のある子など、どんな子でも良いので、1人お友達を作る努力をしてみましょう。
勇気がいることですが、まずはきっかけを探して、お友達に声をかけてみましょう。
親がいじめに対してできるサポート

子供の友人関係の問題に、親があまり首を突っ込み過ぎることは良くないかもしれません。
これも状況や人によって、当てはまること、そうでないことがありますが、いくつかの例を挙げたいと思います。
小さなトラブルの場合
女の子の友達同士の小さなトラブルであれば、相手のお友達に挨拶したり、お菓子をあげたりして、コミュニケーションをとってみることも1つの対処法です。
「いつも、うちの子と遊んでくれてありがとう」
「よく〇〇ちゃんの話を聴いているよ!」
「これからもどうぞよろしくね!」
など、明るくコミュニケーションをとってみるのも良いかもしれません。
本人が言わない場合
本人がいじめられていることを言わない場合も多々あります。
理由はさまざまだと思いますが、親に言うことで、先生に伝わり、その後の更なる報復を恐れている可能性もあります。
どうしても話をしてほしい場合は、学校の先生やお友達には絶対に言わないという固い約束が必要です。
問い詰めること、本人の性格を非難することも絶対にやめましょう。
本人が口を開いてくれた場合は、これまでの努力を認め、打ち明けてくれたことに感謝して、子供の気持ちに寄り添って共感してあげることが一番大切です。
証拠がある場合
教科書やノートに落書きをされたとか、意地悪な手紙をもらったなど、いじめの確かな証拠がある場合は、親が出て良いと思います。
担任の先生に電話をする、お手紙を書いて子供に持たせるなど、事実を伝え、学校側と情報交換や相談を行うべきだと思います。
体調不良や不登校につながる場合
朝起きられない、食欲がない、学校に行くときにぐずるなどの症状が現れると危険信号です。
こういった場合は、あまりヒステリックにならず、冷静に対処しましょう。
まずは、子供さんは、安心で安全な場所を確保したいと考えています。
できるだけ、安心できるようにさせてあげましょう。
そして、担任の先生に連絡、できれば、スクールカウンセラーの先生も交えて相談されるべきだと思います。
対処法に正解はない

多くの例をあげましたが、いじめの状況やいじめる側のタイプ等によって、効果のあるものもあれば、あまり効果のないものもあると思います。
しかし、最も優先すべきは、子供の安全の確保です。
そのためには、子供の心を安全に保てる環境づくり、子供の心が閉鎖的にならないような、安心できる居場所づくりをまずは考えていただきたいと思います。
正しい対処法とか、子育てに正解はありませんが、親の十分な愛情が子供を救うことは間違いありません。
子供の安全と幸せを最優先に考えて、親としてできる限りの誠実な行動をとってゆくことが望ましいと思います。
小学生女子のいじめへの対処法・まとめ

いじめはないに越したことはないですが、万一、子供さんがいじめに遭ってしまった場合、親としては感情のコントロールが難しいと思います。
状況改善のためには、いったん冷静になって事実関係を把握し、子供の安全や幸せを第一に考えて、冷静に、かつ賢く、学校や関係者へ対応をしていただければと思います。