希望に胸を膨らませて、真新しいランドセルを背負って学校に通い始めたのに、いつしか学校へ行くのが苦痛になり、行くのが辛くなってしまった。
子供が「学校に行きたくない」と言い出したら、慌てる親御さんが多いと思います。
なぜ小学校でも不登校になってしまうのか、その原因と、不登校になったときに親として子供に出来る8つのサポートを紹介します。
スポンサーリンク
小学校低学年で不登校になる4つの原因

小学校の1~2年生の場合は、次のような理由が考えられます。
親と離れることが不安
小学校に入ると、朝から午後3時くらいまで学校にいることになります。
その間、親と離れることが不安で、新しい環境になかなか馴染めない子もいます。
特に幼稚園に通っていた子は、保育園に通っていた子と比べ親と一緒にいる時間が長かったため、
- 一人で登校する
- 1日親と離れて過ごす
ということに慣れることが出来ず、学校に行くことが苦痛になってしまう子がいます。
これはどちらかというと男の子の方が多いかもしれません。
学校での集団生活に馴染めない
保育園や幼稚園でも一応集団生活のルールはありますが、その時々で自由にスケジュールを変えられる場合もあり、割と子供に合わせて柔軟に対応してくれます。
その点、小学校はそれが出来ません。
カリキュラムは決まっていますし、一人の都合で全体のスケジュールを変えるわけにはいきません。
また、集団生活のルールも保育園や幼稚園より細かく厳しいものになります。
新しく始まった集団生活に馴染めずに、不登校になってしまう子もいます。
勉強が楽しくない
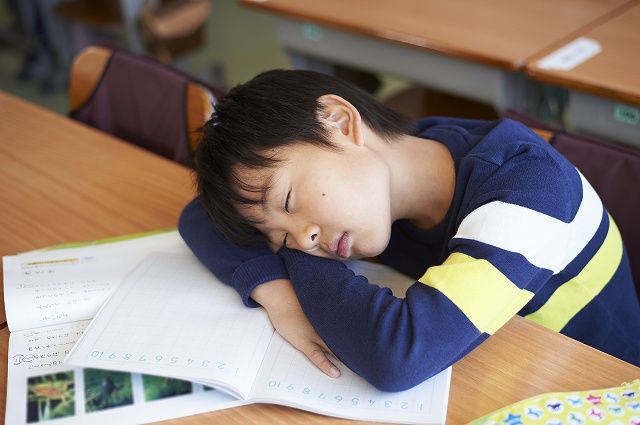
小学校の1~2年生であればそれほど学習内容は難しくないので、しっかり先生の話を聞いていれば、授業についていけないということはあまりないでしょう。
ただ、45分間の授業というのは子供にとって、とても長い時間です。
友達とふざけてしまうとか、集中できないくらいならまだいいのですが、おとなしい子はじっと座ったままその苦痛に耐えていることがあります。
また、2年生になると算数では九九が入ってきます。
この辺りで勉強にも徐々に差がついていくので、基礎的なことでつまづいてしまうと勉強が面白くなくなり、学校にも興味を失ってしまうことがあります。
スポンサーリンク
友達と合わない
小学校の低学年だとまだ「いじめ」という問題は起きにくい年齢ですが、これまでの生活よりもクラスの人数が増える分、どうしても「合わない子」が出てきます。
子供は適応能力があるので、1人くらい合わない子がいても他の子と遊んだりすることができますが、なんとなく居心地が悪かったり、思ったように友達が出来ないことで悩んで学校に行くのがイヤになってしまう子もいます。
子供が不登校になった時に親が出来る8つのサポート

子供には子供なりの理由があるので、不登校になる理由は上記に挙げたものばかりではありません。
子供が学校に行きたくないと言い出したら、親はどんと構えて、慌てずに対処しましょう。
学校を休ませよう
まず、行きたくないというなら学校を休ませましょう。
小学校は出席日数を満たさないと卒業できない、というようなことはありませんので、いくら休んでも大丈夫です。
そのくらいの気持ちでいてください。
無理に行かせても状況は悪化するだけですから、子どもが行きたいという気持ちになるまで行かせない方がいいでしょう。
話をしっかり聞く
子供のことなので、まだ自分の思いをうまく言葉にできないかもしれません。
それでもしっかり向き合って話を聞いてあげてください。
余計な口を挟まずに、ただ子供の話を聞くようにします。
子供は、最初のうちはうまく言えないこともあるでしょうが、親が聞いてくれると思えば安心して段々話すようになってきます。
そうすると、子供自身が「そうか、こういうことが気になっていたんだ」と自分自身で気づくこともあるからです。
原因を探ってみよう

子供と話をする中で、どんなことが原因なのかを探っていきます。
理由は1つとは限らないので、しっかり子供と話して原因を特定することが大切です。
ただし、「理由がない」というケースもあります。
その場合は「何となく行きたくなくなてしまった」ということになりますから、どうすれば行きたいと思えるようになるのか、ということを考えていきます。
ここで「必ず理由があるはずだ」などとさらに追求し、子供を追いつめるようなことをしてはいけません。
学校と対応を相談しよう
不登校になったら、学校との連携は欠かせません。
子供がまた学校へ行きたいと思った時に、スムーズに学校生活に戻れるよう、先生ともよく話し合いましょう。
1~2時間だけの登校にする
保健室登校を認めてもらう
など、その子にとってどのような復帰の仕方がベストか、しっかり話し合ってください。
もし合わない子がいるならなるべく席を離してもらう、場合によってはクラス替えも検討してもらう、ということも考えましょう。
家でできることは?
学校を休んだからといって、家でだらだらと過ごしているのはよくないですね。
1日中ゲームをしたり、マンガを読んでいるのもよくないでしょう。
早寝早起きなど生活のリズムは崩さないようにしましょう。
本を読むとか低学年用のドリルをやってみるなど、勉強の習慣もなくさないようにしたいですね。
一緒に買い物に行くなど、外に出て気分転換をすることも大切です。
共働き家庭だと子供が一人でお留守番することになってしまいますが、短時間であってもシッターサービスを利用して様子を見てもらうとか、一時的に実家を頼るなど、出来る限り子供のサポートが出来るような態勢を整えていきましょう。
親子関係を見直そう

コミュニケーション能力は家庭の中で培われます。
これまで親子の会話が少なかった、親から一方的に話しをしているだけだったなど、何か見直す点はないでしょうか。
合わない子と適度な距離感でつき合うための「コミュニケーション能力」や、人の話を聴く、自分の言いたいことを主張するなどの「バランス感覚」を磨くためにも、親子のコミュニケーションはとても大切です。
もしこれまで子供の話をちゃんと聞いてあげていなかったなと思う点があれば、今日からでも色々な話をしてみましょう。
専門家や経験者から話を聞く
たいていの親御さんは不登校になった経験がないと思います。
ここで常識的な対応をしようとすると、失敗する可能性が高くなります。
理由は様々ですから、その子に適した対応を探るためにはたくさんの経験談を聞き、その中から我が子にあった対策を探っていくというのもひとつの方法です。
場合によっては夫婦でカウンセリングを
親の心が疲れてしまっては子供のサポートを全身全霊で出来ません。
しかし、子供が不登校になる家庭では、夫婦仲に問題のあるケースが少なくないのです。
家庭の基本である夫婦関係にトラブルがあると、子供の話なんて真剣に聞けませんよね。
その場合は、子供の問題の前に夫婦の問題を解決する方が先。
徹底的に話し合うか、場合によっては夫婦でカウンセリングを受けて、夫婦の仲を改善していきましょう。
家庭が子供にとって居心地のいい場所であるようにしてあげてください。
突然不登校になるということはない

子供がある日突然不登校になるということはありません。
それに至る道があったはずです。
具合が悪そうにしているとか、学校のことを段々話さなくなってきていたとか、何かしら兆候があったはず。
毎日の積み重ねで、一つ一つは小さいことだから見過ごされてきてしまったことが、ある日臨界点を超えただけのことです。
小さい子はまだまだ自分の感情を言葉にすることがうまくできないので、いつもと様子が違うところはないか、ご飯はきちんと食べられているか、などを日々見ていかないといけません。
選択肢はいくらでもあるということを忘れずに
でも、不登校になったからといって人生が終わったわけではありません。
親が慌てず、冷静に対処することが大切です。
絶対にいけないのは、無理矢理学校に行かせることです。
よく、「小学校は義務教育だから行かないといけない」と、学校へ通うことを無理強いする親がいますが、義務教育とは親が子供に教育を受けさせる義務のことであり、子供が学校へ行く義務ではありません。
教育の形は1つにこだわる必要はありません。
不登校の子に対する支援を充実させようという動きは確実に増えていますから、まずは子供の心のケアを最優先に、次の進路をどうすることが子供にとって最善の方法なのかということを考えていけばいいことです。
子供が不登校になる原因と対処法・まとめ

大事なことは子供の心と向き合うことと、無理強いをしないことです。
ほんの小さな「学校」という組織の中で子供の可能性を潰してしまってはいけません。
不登校=悪いことというイメージは捨てて、今子供のために何が出来るのか、何をしてはいけないのか、その点に集中しましょう。
