担任の先生にクレームや意見、要望を伝えたいのだけど、連絡帳に書いてもいいのかな?と悩むことはありませんか。
うっかり感情的になって「モンスターペアレント」なんて思われても困ります。
失礼のないように、角が立たないように書くにはどうすればいいか、そのポイントについてお話しします。
スポンサーリンク
角の立たないクレームの伝え方:3つのポイント

クレームを伝えるといいう発想を、ちょっと横において、冷静に事実確認をすることを目的に書きましょう。
事実確認というスタンスで書く
まず、クレームを伝えるのではなくて、あくまでも、何がおきたのかの確認をしてもらうという、事実確認をしたいというスタンスで話をしましょう。
そして、あくまでも先生にご相談があります、という書き方で進めると、角が立たないと思います。
クレームではなくて、あくまでも相談
例えば、誰かに意地悪をされたと自分の子供が訴えてきたとします。
その事実を先生が知っているのか、知らないのか、それによっても話が変わってきますから、まず何があったのかを確認してもらうことが大事です。
もしも子供がその時に先生に相談しているのであれば、「子供からこのような話を聞きましたが、私の認識で合っているでしょうか」と聞きましょう。
子供が先生に相談していなかったら、そもそも先生がその事実を知らない可能性があるので、「子供がこのように話しているのですが、なぜそうなったのか知りたい」と相談します。
その返事によって、問題解決のためには今後どうしたら良いのかと相談する形にするのがベストです。
夫婦で共有する
ママが勢いで書いたものをそのままで提出することはやめて、パパにも見てもらいましょう。
それは、誰かに見てもらうことで、客観的に書けているか、先生を責めるような文章になっていないかを確認できるからです。
また、何が起きたのか、子供がどう言っているのかをパパもママも聞き、今後どう進めていくのかを二人で話し合い、共通の認識を持ってから、連絡帳を提出しましょう。
スポンサーリンク
角の立たないクレーム書き方【文例】
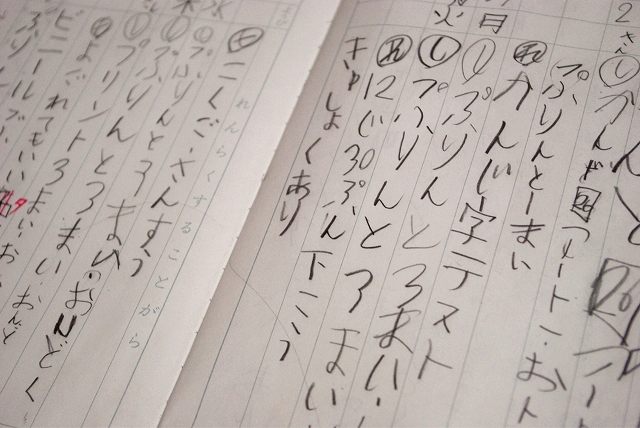
それでは、実際にどう書くべきか、書き方についてご紹介します。
挨拶は必須
基本的な書き方はビジネス文書と一緒で、まずは挨拶です。
-
いつも子どもがお世話になっております
-
本日はお聞きしたいことがありまして連絡帳を書きました。
いきなり文句から始めないように気をつけてください。
友達とのトラブルの場合の書き方
友達の喧嘩など珍しいことではありませんが、先生が知らないところでおきていることもよくあります。
まずは本当にその事実があるのかと、なぜそうなったのかを確認してもらいましょう。
「子供が○○くんにいきなり殴られたと話しています。何もしていないと本人は言っておりますが、子供の言うことなので前後関係がわかりません。本当にそのようなことがあったのか、相手の子も交えて事実の確認をしていただけないでしょうか。また、本当だった場合は何があってそんなことになったのかも確認していただけないでしょうか。」
トラブルが起きた理由次第で、以下のように、対応が違ってきます。
-
相手の子に謝ってもらう
-
こちらにも非があったのでお互いに謝る
事実確認をしっかりした上で、仲直りができると良いですね。
学校になじめてないと感じる場合の書き方
具体的に何かあったのかは話していないけれど、何となく子供の様子が気になることもありますね。
先生はちゃんと見てくれているのかしらと心配になると思いますが、こういった場合にも、やんわりと聞くことを心がけます。
「最近家で少し元気がないような時があります。学校での話をあまりしてくれないので、学校での様子を知りたいです。クラスでの様子はいかがでしょうか。何か変わったことはないか、先生がお気づきのことがあれば教えていただけないでしょうか」
勉強についていけない不安がある場合の書き方
子供が、勉強についていけているかどうかが心配になることもあります。
自分が真面目にやっていないのに、「先生の教え方がわからない」などと親に話す子もいます。
そのような時でも、クレームにならないように気をつけましょう。
「算数のくり下がりの引き算が苦手なようです。学校での様子はどうでしょうか。授業についていけているか、授業中はきちんと話を聞けているでしょうか。家でも気をつけるべきことがあれば教えていただくと助かります。」
子供が先生の悪口を言っている場合の書き方
子供が「先生にこんなことを言われた」「先生にこんなことをされた」と、先生に対する文句を言っている場合は、子供の言っていることだけで判断することができないため、先生の言い分も知りたいというスタンスが良いでしょう。
「子供が先生に『~~~』と言われたと話をしています。どのような状況でそのような話になったのか、子供の話だけでは前後関係がわかりませんので詳しく教えていただけるとありがたいです。」
「子供から『~~~』ということがあったと聞いております。我が家では普段『~~~』ということを話しておりますので、子供としては少々戸惑いがあるようです。その時の状況や先生のお考えをもう少し詳しくお聞きしたいと思っています。」
子供の話だけを鵜呑みにしない

これが一番大事なのですが、自分の子供の言うことだけを鵜呑みにしないということです。
小学校の低学年の子どもが、実際に起こった出来事について、何が起きたのかを正確に親に伝えられる子供は少ないと思います。
-
「私は何もしていないのに、○○くんがいきなりぶったんだよ!」
-
「僕は何もしていないのに、○○くんが悪口を言ったんだ」
子供は、自分のことを棚に上げて、上記のようなことをよく言いますが、実際は、自分に原因があったりすることもよくあります。
このような場合は、決して嘘をついているわけではなく、本当にそう思って言っている可能性がありますので、子供を怒っても仕方ありません。
大事なことは、前後関係を知ることと、実際にどんなことがあったのか事実を把握することです。
ですから、子供の言うことを鵜呑みにして「先生に文句を言わないと!」と思ってそのままを書くと、恥をかくことになるので気をつけましょう。
まとめ

幼稚園や保育園と違って毎日先生と顔を合わせているわけではないので、クレームがあったとしてもまずは信頼関係を築くことが大切です。
先生との信頼関係を築くことができれば、何かあっても相談しやすくなりますから、くれぐれもクレームではなく「相談」というスタンスで話をするようにしましょう。
